工場の安全管理は、従業員の生命と健康を守り、安定した事業継続を実現するための最重要課題の一つです。その中でも、見落とされがちながら極めて重要なのが「電気設備の定期点検」です。
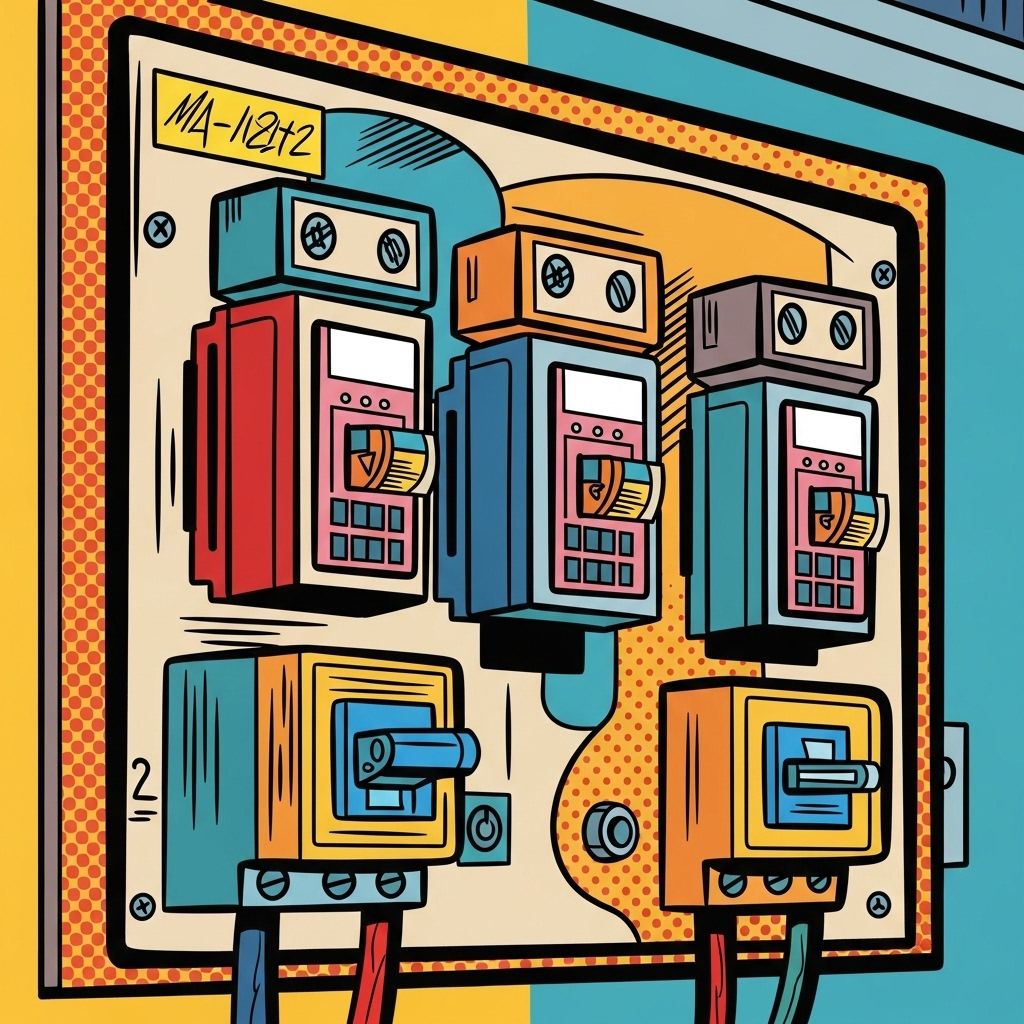
「専門的なことは設備管理部門に任せているから…」とお考えの担当者様も多いかもしれません。しかし、万が一事故が発生した場合、その影響は工場全体、ひいては会社全体の経営問題に直結します。
今回は、人事・労務担当者としても知っておくべき、工場の電気設備の法定点検について、その頻度や重要性を分かりやすく解説します。
目次
そもそも、なぜ点検が必要?根拠となる法律とは
まず、法律で点検が義務付けられているのは、電力会社から高圧または特別高圧で電気の供給を受ける設備、いわゆる自家用電気工作物です。多くの工場がこれに該当し、電気事業法という法律で定期的な点検が企業の重要な責務として定められています。
これは、自社の安全を守るだけでなく、周辺地域を巻き込む大規模な停電(波及事故)を防ぐという社会的な責任も担っているためです。
法律で定められた点検は2種類!その頻度と内容は?
法律で定められた点検には、大きく分けて2つの種類があります。それぞれ見ていきましょう。
① 月次点検(毎月1回以上)
~日常の”健康診断”で異常のサインを見逃さない~
毎月1回以上、専門家(電気主任技術者)が工場の電気を止めずに実施する点検です。
設備の異音や異臭、異常な発熱がないかなど、いわば日常的な”健康診断”にあたります。これにより、トラブルの初期症状を早期に発見することが目的です。
② 年次点検(毎年1回以上)
~停電して行う”精密検査”で事故を未然に防ぐ~
年に1回以上、原則として工場の電気を止めて(停電させて)行う、より詳細な点検です。人間でいえば”精密検査”にあたります。
普段は見られない機器の内部まで点検し、絶縁状態や安全装置が正常に機能するかを専門的にチェック。これにより、火災や感電といった重大事故を未然に防ぎます。
<Point>
24時間稼働の工場など、やむを得ない事情で停電が難しい場合は、国の承認を得ることで年次点検の周期を延長できる特例もあります。ただし、その場合も別の方法で精密な点検を行う必要があります。
「うちの工場は大丈夫」は危険!
点検を怠ることによる3つの重大リスク
もし、法定点検を適切に実施しなかった場合、企業はどのようなリスクを負うのでしょうか。
- リスク1:従業員の安全を脅かす(労働災害)漏電やショートによる感電・火災は、従業員の生命を直接脅かす重大な労働災害につながります。安全配慮義務の観点からも、決してあってはならない事態です。
- リスク2:事業停止による莫大な損失(生産機会の損失)大規模な停電や火災が発生すれば、工場の操業はストップ。復旧までの生産機会の損失や、納期遅延による取引先からの信用失墜は計り知れません。
- リスク3:近隣を巻き込む「波及事故」(社会的信用の失墜)工場の電気事故が原因で、地域の広範囲な停電(波及事故)を引き起こす可能性があります。自社だけでなく、社会全体に多大な迷惑をかけ、企業の社会的信用を大きく損なうことになります。
■ まとめ:安全管理は全社で取り組むべき経営課題
工場の電気設備の定期点検は、法律で定められた義務であると同時に、従業員と会社を守るための重要なリスクマネジメントです。
人事・労務担当者としても、こうした法定点検が適切に実施されているか関心を持つことが、職場全体の安全文化を醸成する上で非常に大切です。これを機に、自社の設備管理体制について、担当部署とコミュニケーションをとってみてはいかがでしょうか。